歯科医院に通う患者さんの多くが、こう考えているかもしれません。
「歯医者に行けば、どんな歯の問題もきれいに治してもらえるはずだ」と。
確かに、虫歯の治療や歯石除去、歯並びの矯正、インプラントなど、現代の歯科医療は飛躍的に進化してきました。しかし実際のところ、どんなに医学が進歩しても“完全には治せない”病気が、歯科にはいくつか存在します。
今回は、「歯科における“治せない病気”とは何か?」「なぜ治らないのか?」「それでもできることはあるのか?」という疑問に対して、わかりやすく解説していきます。
完治が難しい歯科の代表的な病気
1. 歯周病(進行した慢性歯周炎)
歯周病は、日本人が歯を失う原因の第1位です。歯ぐきの中で進行するこの病気は、歯を支える骨(歯槽骨)を徐々に破壊していきます。
一度骨が溶けてしまうと、完全な再生は非常に難しく、一時的に治ったように見えても再発することがあります。しかも原因となる歯周病菌は、口の中に常在するため完全に排除することはできません。
【対処法】
- 定期的なクリーニング
- 歯周ポケットの管理
- 重度の場合は歯周外科や再生療法
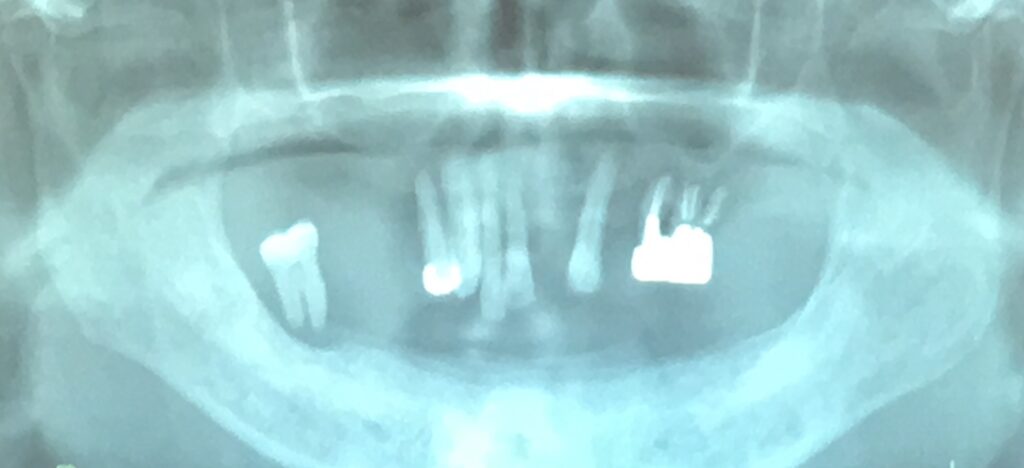
2. 歯の神経を取った歯(失活歯)
虫歯が深く進行すると、神経(歯髄)を除去する「根管治療」が必要になります。これによって痛みはおさまりますが、神経を取った歯は栄養や水分が行き届かなくなり、もろくなるというデメリットがあります。
つまり、どれだけ精密に治療しても、元の健康な歯のような強さや寿命は戻らないのです。
【対処法】
- クラウン(被せ物)で補強
- 二次感染を防ぐための丁寧な管理
- 抜歯を避けつつ、使える限り使う

3. 歯根破折(歯の根が割れる)
歯の根っこが縦に割れてしまうと、それをくっつけて治すことはほぼ不可能です。特に見えない部分で亀裂が入っていると、症状が進行してから発見されることもあり、最終的には抜歯になるケースがほとんどです。
【対処法】
- インプラントやブリッジによる補綴治療
- 早期発見ができれば、短期的な保存処置も
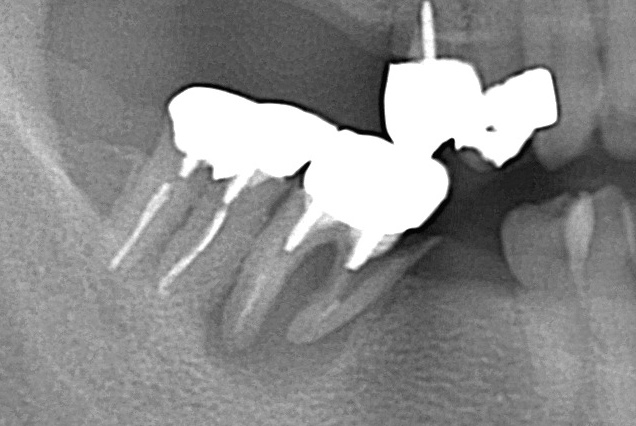
4. 根尖病変が治らないケース(難治性根尖病巣)
根の先に膿がたまる「根尖病変」は、通常は根管治療で治りますが、感染源が複雑な場合や、歯根の形が特殊な場合には何度治療しても治らないことがあります。
こうした場合、外科的に根の先を切除する「歯根端切除術」などが必要ですが、それでも改善しないこともあります。
【対処法】
- 再根管治療
- 外科処置
- 最終的に抜歯の判断も視野に

5. 先天性の歯の形成異常や欠損
- 歯の本数が足りない「先天性欠如」
- エナメル質や象牙質がうまく形成されない「形成不全」
こういった遺伝的要因による歯の異常は、根本的に治すことはできません。特に成長期のお子さんでこうした問題があると、審美性や機能性への配慮が求められます。
【対処法】
- 補綴(被せ物、ブリッジ、義歯など)
- 矯正治療との併用
- 長期的な経過観察

6.虫歯が大きすぎて修復不能
虫歯が大きすぎると、虫歯を除去した後の残りの健全な部分が少なくなります。被せ物などで修復するにしても残りが少なすぎると修復が不可能な場合もあります。
対処法:抜歯

「治らない=諦める」ではない
「治らない」と聞くと、絶望的に思えるかもしれません。しかし実際には、「治らないけれど進行を止める」「症状をコントロールする」「機能的に維持する」ことは十分可能です。
例えば、糖尿病や高血圧といった生活習慣病と同じように、歯科でも**「うまく付き合っていく病気」**があるということです。
まとめ:歯は一度壊れたら“元通り”には戻せない
歯科医療は確実に進歩していますが、「削った歯が自然に戻る」「失った歯が勝手に生えてくる」ことはありません。だからこそ、
- 予防が最も重要
- 早期発見・早期対応が鍵
- 治らなくてもコントロールできる
という考え方がとても大切です。
「この病気はもう治らない」と言われても、適切な処置とメンテナンスを続ければ、長期間しっかり噛める状態を維持することができるのです。
歯のことで悩んでいる方へ
もし今、歯やお口のトラブルで悩んでいるなら、一人で悩まず、まずは歯科医院で相談してみてください。
「治せない」と言われた病気でも、「どう付き合えばいいか」「どんな方法があるか」まで、丁寧に説明してくれる歯科医師がきっといます。

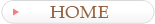
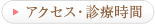
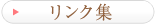


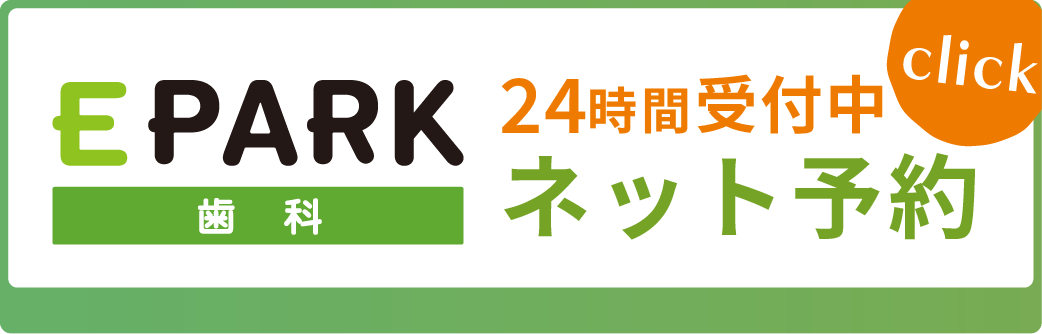

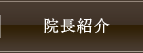
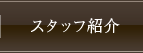
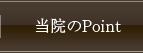
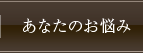
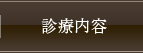
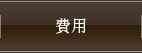
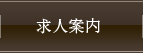

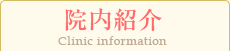


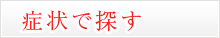
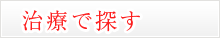

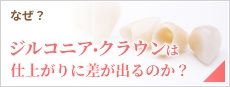


 当院のInstagramはこちら
当院のInstagramはこちら