虫歯の治療に関して、患者さんが複数の歯科医に相談すると、それぞれ全く異なる見解を示されることがあります。
- 「すぐに削って詰めた方がいいです」
- 「この程度なら経過観察でも大丈夫」
- 「神経は早めに取った方が安心です」
- 「いや、神経は残せます」
これらはすべて、実際の診療現場でよく起こる現象です。では、なぜ歯科医によってこれほどまでに治療方針が分かれるのでしょうか?本記事では、その理由をいくつかの視点から詳しく解説します。
1. 虫歯は「進行性の病気」だが「止まる」こともあるから
虫歯(う蝕)は基本的に進行性の病気です。放っておけば象牙質に進行し、やがて歯髄(神経)にまで達する可能性があります。しかし一方で、初期の虫歯(特にエナメル質内にとどまるもの)は、歯磨きやフッ素塗布などのケアによって進行が抑えられることもあります。
そのため──
- 進行性だと考える歯科医は「早期治療」派
- 進行を抑えられると考える歯科医は「様子見」派
となるのです。
特に、エナメル質の虫歯は削らなくても進行しないことがあるため、「要観察歯」として管理されることもあります。しかし逆に、表面上は小さくても中で大きく広がっている虫歯も存在するため、慎重派の歯科医は「小さいうちに治療すべき」と判断することになります。

2. 「削ること」に対する哲学の違い
虫歯の治療では、虫歯に冒された歯質を削り取り、詰め物や被せ物で補います。しかし、削るという行為は一度きりで後戻りができず、将来的に歯を弱くする可能性も含んでいます。
そのため──
- できるだけ歯を削らず残したい=「MI(Minimal Intervention)」を重視する歯科医は様子見や経過観察を提案
- 将来的な再治療を防ぐために確実に処置したい歯科医は早期に削る判断をする
というふうに、治療哲学によって判断が分かれます。
MI治療を志向する歯科医は、「できる限り削らないこと」自体が治療の目的となるため、極力慎重な対応を取ります。一方で、二次カリエス(詰め物の下に再発する虫歯)や破折のリスクを避けたい歯科医は、積極的に治療介入を行う傾向があります。
3. レントゲンや肉眼所見の解釈に「グレーゾーン」がある
虫歯の進行度を把握する手段としてレントゲンがありますが、その読影は主観が入りやすく、100%の正解はありません。
また、肉眼での視診においても「表面に穴がない=進んでいない」とは限りません。内部で虫歯が進行しているケースもあり、歯科医の経験や判断力が大きく関与します。
このため──
- 「進んでいる可能性がある」と考える歯科医は即治療
- 「まだ浅い」と考える歯科医は経過観察
と、同じ症例を見ても判断が分かれるのです。

4. 患者の生活背景や希望が関係することも
虫歯の進行や治療計画は、患者の生活状況や希望によっても左右されます。
たとえば:
- 海外赴任予定がある → 早めに治療を終えたい
- 妊娠中で薬や麻酔を控えたい → なるべく削りたくない
- 通院が困難な高齢者 → 1回で済ませたい
このように、「歯の状態だけ」でなく「人としての背景」も含めて判断する必要があり、それが歯科医の評価に影響を与えるのです。
5. 「神経を取る」「取らない」の分かれ道は特に評価が割れる
神経(歯髄)を残すかどうかの判断は、非常にセンシティブな問題です。神経が残っていれば歯は生きた状態を保てますが、痛みや炎症の再発リスクもあります。
一方で神経を取れば、歯の痛みは治まりますが、歯がもろくなりやすく、将来的に破折や抜歯リスクが高まります。
よって──
- 再発リスクを避けるために「早めに神経を取る」派
- 歯の寿命を重視して「できるだけ残す」派
という意見の分かれが生じやすいポイントなのです。
6. 歯科医の経験値やスタイルの違い
実は、虫歯の評価が分かれる背景には、歯科医自身の臨床経験や教育を受けた環境の違いもあります。
- 開業医で即決即治療スタイルを身に着けた先生
- 大学病院で慎重に診断を重ねるスタイルを重んじる先生
- 保険診療と自由診療で治療アプローチが異なるケース
このように、**「正解が一つではない領域」**では、治療方針が個々の歯科医によって大きくブレるのです。
7. 患者としてどう判断すればよいか?
ここまでを読むと、「結局、誰の言うことを信じればいいの?」という疑問が湧くかもしれません。
その答えはシンプルで、「自分の希望を正直に伝えた上で、それに合った説明をしてくれる歯科医を選ぶこと」です。
- 将来長く歯を残したいのか?
- とにかく痛みなく早く治したいのか?
- 経過観察に納得できるのか?
治療方針に「絶対の正解」はないからこそ、患者と歯科医のコミュニケーションが最も重要になります。
まとめ:評価が分かれるのは当然、だから「対話」が大切
虫歯治療において「すぐ治療」「経過観察」「神経を取るか否か」などの評価が分かれるのは、病気の性質、医師の哲学、診断手法、そして患者背景がそれぞれ異なるからです。
現代の歯科治療では、医学的根拠だけでなく、患者の価値観を反映した選択が推奨されています。そのためにも、どんな治療にもリスクとベネフィットがあることを理解し、納得できる選択をすることが大切です。
迷ったときは、複数の歯科医に相談してみるのも一つの方法です。その中で、自分が一番信頼できる先生を見つけてください。

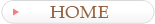
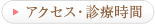
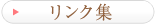


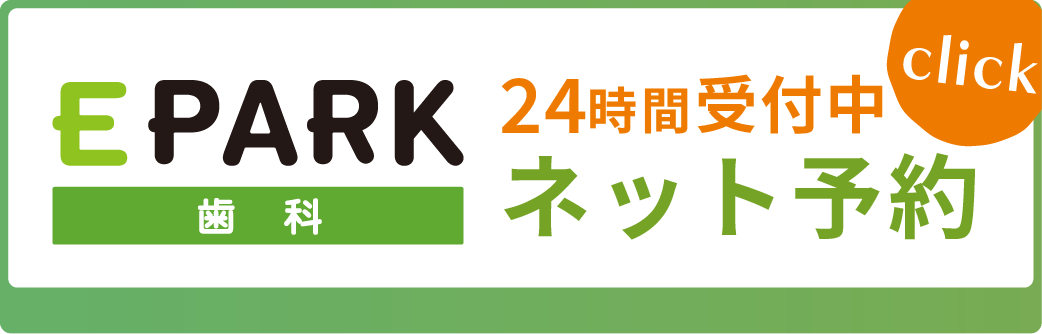

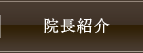
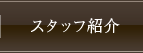
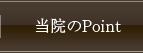
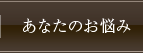
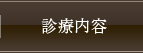
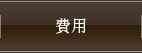
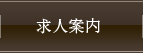

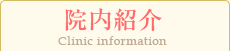


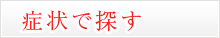
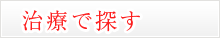

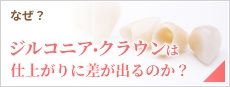


 当院のInstagramはこちら
当院のInstagramはこちら