〜治療の限界と「骨が戻らない」現実〜
歯周病は「沈黙の病気」と呼ばれ、自覚症状が出たときにはすでに進行しているケースが少なくありません。歯ぐきの腫れや出血から始まり、やがて歯を支える骨(歯槽骨)が吸収されていき、放置すれば最終的に歯が抜けてしまう病気です。
では、この恐ろしい歯周病は完全に「治す」ことができるのでしょうか?
今回は、歯周病の治療の現実、そして特に「骨レベルはなかなか戻らない」という歯周病治療の限界について、分かりやすく解説していきます。
歯周病とはどんな病気?
まず、歯周病の正体を簡単におさらいしておきましょう。
歯周病とは、歯と歯ぐきの間にたまったプラーク(細菌の塊)によって、歯ぐきに炎症が起こり、進行すると歯を支える骨(歯槽骨)までもが溶けてしまう病気です。
初期段階は「歯肉炎」と呼ばれ、歯ぐきに炎症があるものの骨はまだ溶けていません。この段階であれば、歯みがきや歯科医院でのクリーニングで比較的容易に治すことができます。
しかし、骨が溶け始めた「歯周炎」に進行してしまうと、状況は一変します。

「治る」とはどういうことか?
医療において「治る」とは、病気になる前の状態に戻ることを指すのが一般的です。
風邪を引いても、治れば元どおりになります。骨折しても、適切な治療と時間があれば骨はくっつき、ほとんど元通りに動けるようになります。
では、歯周病で失われた「骨」は元通りになるのでしょうか?
答えは、「基本的には戻らない」です。
なぜ歯周病で失われた骨は戻らないのか?
歯を支える骨(歯槽骨)は、一度吸収されてしまうと自然に再生することはありません。歯周病が進行して歯周ポケットが深くなり、炎症が慢性的に続くと、骨が少しずつ溶かされていきます。
いったん骨が失われた部分には、「空洞」ができます。しかし、体にはその空洞を埋め戻す力はほとんどありません。傷ついた皮膚のようにはいかないのです。
これは、歯周病が細菌感染による「慢性炎症性疾患」であるという特徴が関係しています。細菌が常に存在し、炎症を繰り返す環境では、骨の再生は阻害されてしまうのです。

治療のゴールは「元に戻す」ではなく「進行を止める」
したがって、歯周病治療の目標は「歯を支えている骨を再生する」ことではなく、「これ以上悪化させないこと」に置かれています。
歯科医院での歯石除去や、歯周ポケット内の徹底的な洗浄、そして患者さん自身のセルフケアの徹底が、治療の基本です。
これによって、歯ぐきの腫れや出血は改善し、歯周ポケットも浅くなり、進行は止まります。しかし、すでに失われた骨が完全に戻ることは、極めて難しいのです。
骨を再生させる治療もあるが…
近年では、「再生療法」と呼ばれる特殊な治療法も登場しています。たとえば以下のようなものです。
- エムドゲイン法:骨の再生を促す薬剤(エムドゲイン)を使う方法
- GTR法(組織再生誘導法):人工膜を使って骨の再生スペースを確保する方法
- 骨移植:患者自身の骨や人工骨を移植する方法
これらは、失われた骨の一部を再生できる可能性がありますが、適応症が限られていたり、結果にばらつきがあったり、高額な自費治療であることが多いです。また、完全に元の骨レベルに戻るケースは極めて稀です。
歯周病は「コントロールする病気」
歯周病は「完全に治す」というよりも、「コントロールして共存する」病気と考えたほうが現実的です。
たとえば高血圧や糖尿病のように、治療によって症状が安定していても、油断すれば再び悪化してしまう。歯周病も同様に、セルフケアや定期的なメンテナンスが不可欠なのです。
歯周病をコントロールするために大切なこと
- 毎日の歯みがきの質を高める
歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシも使うことが重要です。 - 定期的なプロフェッショナルケア
歯科医院でのクリーニング(PMTC)や歯周ポケットのチェックは、最低でも年に2〜4回受けましょう。 - 生活習慣の改善
喫煙やストレスは歯周病の大敵。全身の健康も意識しましょう。
「治ったように見えても、油断は禁物」
歯ぐきの腫れが引き、出血が止まり、「もう治ったかな」と思ってしまう方も多いですが、これは「表面的に落ち着いているだけ」の可能性があります。
一度失われた骨が戻っていない以上、歯周病の再発リスクは常にあります。むしろ、良くなったときこそ「メンテナンス期のスタートライン」と言えるでしょう。
まとめ:歯周病は「治らないが、止められる病気」
歯周病は、初期のうちに適切なケアをすれば改善が期待できますが、骨が失われてしまった場合には完全に元通りにはなりません。
しかし、進行を食い止め、症状をコントロールし、再発を防ぐことは十分可能です。
「歯周病は治らない」と聞くとショックを受ける方も多いかもしれませんが、「一生付き合っていける病気」と考えれば、前向きに取り組めるのではないでしょうか。
自分の歯を1本でも多く残すために、今日から「歯周病と上手につきあう生活」を始めましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な治療方針については、かかりつけの歯科医師にご相談くだ

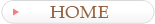
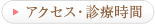
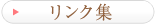


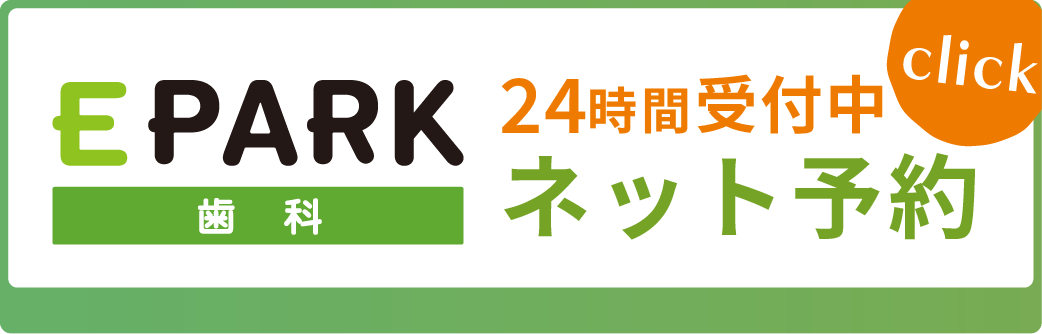

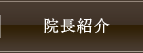
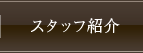
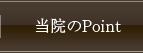
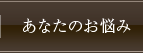
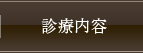
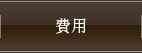
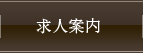

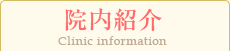


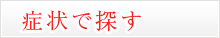
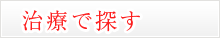

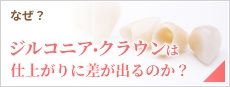


 当院のInstagramはこちら
当院のInstagramはこちら