総義歯(いわゆる入れ歯)は、歯を失った方が再び快適な食事や会話を楽しむために欠かせない補綴装置です。中でも上顎(じょうがく)の総義歯は、義歯が落ちたり外れたりしやすいという悩みが多く聞かれます。しかし、正しい設計・調整・装着がなされていれば、義歯はしっかりと上顎に吸着し、安定した機能を果たすことができます。
本記事では、「上顎の総義歯が落ちないように歯科医師が気を付けていること」をテーマに、臨床現場での工夫や注意点を解説します。総義歯に不安を感じている方、これから作る予定のある方にとっても、有益な情報となるはずです。
1. 義歯が落ちる主な原因とは?
まず、なぜ上顎の総義歯が落ちやすいのかを知ることが重要です。以下のような原因が挙げられます。
- 吸着力の不足(陰圧が弱い)
- 義歯床(ぎししょう)の適合不良
- 咬合圧の不均衡
- 口腔内の粘膜や骨の状態が悪い
- 唾液量の不足や性状の変化
- 舌や頬の動きによる義歯の浮き上がり
これらを踏まえて、歯科医師は診査・設計・製作の段階から多くの工夫を凝らしています。

2. 印象採得(型取り)の精度が命
義歯の土台となる「義歯床」が口の粘膜にぴったり合っていることは、安定性に直結します。そのため、歯科医師は「精密印象」と呼ばれる工程で、非常に正確な型取りを行います。
特に上顎の場合、義歯が吸盤のように口腔粘膜に吸着するためには、口蓋(こうがい)部分の密閉性が重要です。このために、
- 個人トレーの作製
- 機能印象(患者さんが実際に口を動かしながら型を取る方法)
- 粘膜の動きを考慮した印象材の選択
など、複数のステップと技術が必要です。

3. 咬合(こうごう)調整で噛み合わせのバランスを整える
義歯が落ちる大きな要因として、不安定な咬み合わせがあります。噛むたびに義歯が揺れてしまえば、上顎の義歯はすぐに外れてしまいます。
歯科医師は、以下の点に細心の注意を払います。
- 咬合平面の設定(義歯の水平バランス)
- 咬合高径の確認(上下の義歯が適切に当たる高さ)
- 中心位(ちゅうしんい)の正確な記録
- 咀嚼時の偏りを防ぐ設計
これらを実現するために、咬合器という装置を用いて模型上でシミュレーションを行い、最終義歯を調整していきます。

4. 唇・頬・舌の動きを読む
口の中は、静止しているわけではありません。話す、食べる、笑うといった動作のたびに、唇や頬、舌が動きます。これらの動きが義歯に干渉してしまうと、義歯は外れてしまいます。
歯科医師は、機能印象の際にこれらの動きを観察・記録し、以下のような工夫をします。
- 義歯の縁(ふち)の長さや厚みの調整
- 頬筋・口輪筋との調和
- 吸着線(post dam)の形成
このような細かな工夫が、装着時の安定性に直結します。
5. 唾液の影響も無視できない
唾液は、義歯の吸着に大きく関わる要素です。上顎の義歯は、粘膜と義歯床の間にある唾液によって「陰圧」が生まれ、吸着力が得られます。しかし、ドライマウスなどで唾液量が少ない場合、義歯がうまく吸着しません。
こうしたケースでは、
- 唾液腺マッサージの指導
- 保湿剤や口腔ジェルの使用
- 義歯粘膜面の形状調整による陰圧強化
など、患者さん一人ひとりに合わせた対応を行います。
6. 使用後の調整とアフターケア
いくら精密に作られた義歯でも、口腔内の状態は常に変化しています。使用後に「落ちやすい」「痛い」といったトラブルが起きることもあります。
歯科医師は、次のようなフォローアップを丁寧に行います。
- 圧痛部位の調整
- 義歯安定剤の正しい使用法の説明
- 再適合(リライニング)による調整
- 定期的な咬合チェック
患者さんの使用状況を見ながら、義歯の状態を常に最適に保つことが求められます。
まとめ:技術と観察力が支える「落ちない義歯」
上顎の総義歯を「落ちにくく」「快適に」保つためには、歯科医師の技術、観察力、そして患者さんとのコミュニケーションが不可欠です。単に「合わないから外れる」のではなく、そこには多くの要素が複雑に関係しています。
義歯に不満を感じている方、これから作成を検討している方は、ぜひ信頼できる歯科医院で相談してみてください。そして、「調整は当たり前」「使いながら完成度を高めるもの」と考え、積極的にアフターケアを受けることが、満足のいく義歯生活への第一歩です。

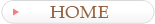
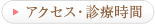
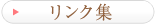


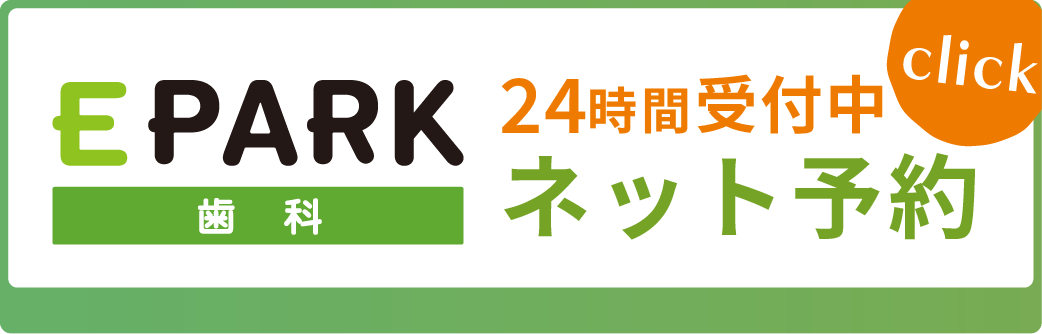

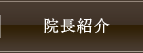
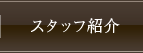
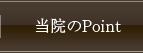
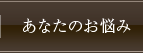
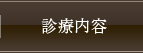
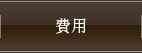
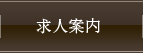

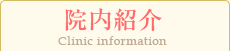


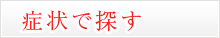
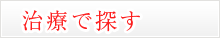

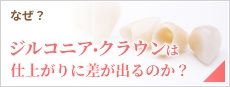


 当院のInstagramはこちら
当院のInstagramはこちら