~割れやすさと“2年保証”の制度の狭間で~
歯科医院に行って、「保険の白い歯でお願いします」とお願いしたことのある方も多いのではないでしょうか。最近では、保険診療でもある程度白くて見た目のよい「CAD/CAM冠(キャドカムかん)」という歯が認められており、金属の歯ではなく自然な見た目を希望する患者さんにとってありがたい選択肢となっています。
しかし一方で、患者さんが「保険のCAD/CAM冠を入れてください」とお願いしても、あまり乗り気でない歯科医師もいます。中には「割れやすいですよ」「やめた方がいいですよ」と強く勧めてこない先生もいます。
なぜ歯科医師の中には、保険CAD/CAM冠に消極的な人がいるのでしょうか?
実は、その理由にはCAD/CAM冠の素材的な弱点や、制度上の負担、さらにはトラブル対応の義務といった背景があるのです。

CAD/CAM冠とは?
まず、CAD/CAM冠というのは、「CAD(Computer-Aided Design)」と「CAM(Computer-Aided Manufacturing)」というデジタル技術を使って作られた、プラスチックとセラミックの中間のような素材の被せ物です。歯の型をスキャンし、そのデータをもとにミリングマシンで削り出すことで製作されます。
見た目は白く、銀歯に比べれば圧倒的に自然で、金属アレルギーの心配もありません。これが保険でできるようになったのは、2020年頃からです。
実は「割れやすい」という素材の問題
CAD/CAM冠の最大の弱点は、「割れやすさ」です。素材自体はハイブリッドレジンと呼ばれるもので、金属やセラミックと比べると強度が低く、経年劣化もしやすいのです。
特に、強い咬合力がかかる奥歯(大臼歯)では割れる確率が高くなるため、保険適用にも制限があります(たとえば上下左右の第二大臼歯には原則として使用できません)。注!1年ほど前から適用になりました。
患者さん側からすると、「せっかく白い歯にしたのに1~2年で割れた」という事態が起こることも少なくなく、結果的に再治療となります。
「2年間は再製作無料」? 保険制度の落とし穴
さらに歯科医がCAD/CAM冠を敬遠する大きな理由に、「2年間の再製作義務」があります。
健康保険のルールでは、一度保険で作った冠は2年以内に壊れても、原則として再び保険での請求ができません。つまり、**2年以内に割れた場合は、医院が“無料で作り直さなければならない”**のです。
これが非常に大きなリスクになります。
CAD/CAM冠が1年半で割れた、という患者さんが来たとき、歯科医院としては再製作のコストと技工料をすべて自己負担でやり直すことになり、利益どころか赤字になることさえあります。
保険点数と手間のバランスが悪い
CAD/CAM冠は、保険で1本約8000〜10000円程度(医院の収益として入る分)ですが、実際には
- 技工所に支払う技工料(5000〜6000円)
- 材料費
- 事務コスト
- 再診料等を除いた人件費
を考えると、医院の利益は非常にわずか。しかも、万が一割れた場合の「タダでやり直し」のリスクを考えると、やりたがらないのも無理はないのです。
トラブルの温床にもなりやすい
さらに、割れたり脱離したりするトラブルが起きたとき、患者さんが不信感を抱くこともあります。
「なんで割れるの?」
「先生のやり方が悪いんじゃないの?」
とクレームを受けることもあり、医院の評判や信頼に関わる問題に発展するケースも。
そのため、最初から「自費のセラミックにしませんか?」と勧める先生も少なくありません。もちろん、セラミックの方が審美性も耐久性も上ですが、費用は1本8〜15万円程度と大きく異なります。

患者さんにとって大事なことは「理解」
こうした背景を知っておくと、歯科医師がなぜ「保険CAD/CAM冠」を積極的にすすめないかが見えてきます。
もちろん、CAD/CAM冠がダメな材料というわけではありません。適切な場所に使い、咬合調整を丁寧に行い、患者さんにもリスクを伝えたうえで装着することで、十分な期間もたせることも可能です。
しかし、それでもリスクはゼロにはなりません。だからこそ、「保証のない保険治療」であるCAD/CAM冠において、割れるリスクと2年保証という制度のはざまで、歯科医は常に“板挟み”の状態にあるのです。
まとめ:白い歯は万能ではない
保険のCAD/CAM冠は確かに魅力的です。しかし、材質的な制限や制度上の負担を理解したうえで使う必要があります。
もし歯科医師がやんわりと「やめた方が…」と言ってきたとしたら、それは単なる金儲けのためではなく、患者さんに長く快適に使ってもらうための誠実な判断かもしれません。
「見た目」と「耐久性」、そして「費用」のバランスをよく理解し、納得した治療選択をすることが大切です。


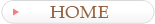
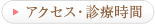
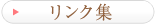


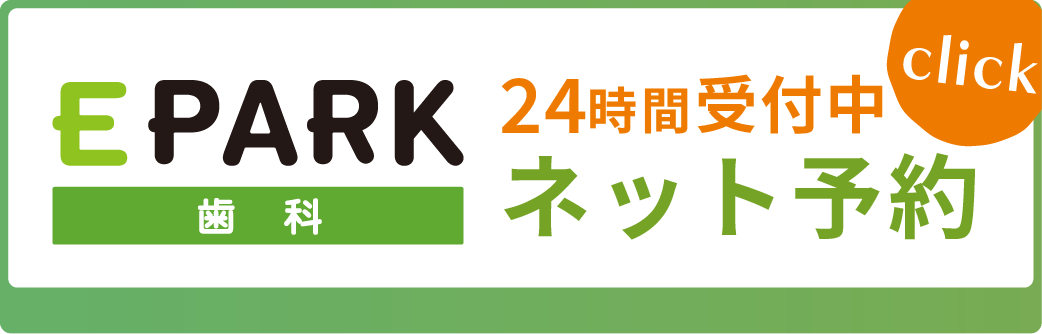

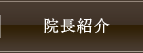
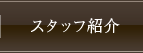
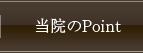
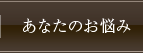
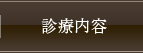
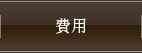
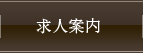

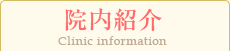


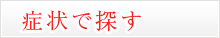
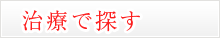

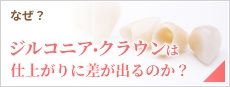


 当院のInstagramはこちら
当院のInstagramはこちら