糖尿病は、血糖値のコントロールが困難になる慢性的な代謝疾患です。現在、日本では1000万人以上が糖尿病を患っているとされており、さらにその予備群も含めると2000万人を超えるといわれています。糖尿病は全身の健康に深刻な影響を及ぼす疾患ですが、実は歯科治療の現場でも非常に大きな問題になることがあります。
本記事では、「糖尿病の程度によっては通常の歯科治療がはばかられる場合がある」という事実について、医療的な背景とともにわかりやすく解説します。
なぜ糖尿病が歯科治療に影響を与えるのか?
糖尿病が歯科治療に影響を与える主な理由は以下の3点です。
1. 傷の治りが遅くなる
糖尿病では血糖値が高くなることで、末梢血管の血流が悪化します。その結果、体の組織に酸素や栄養が届きにくくなり、傷の治癒が遅れるのです。歯科治療では抜歯やインプラント手術など、粘膜や骨に侵襲を加える処置が少なくありませんが、糖尿病患者の場合、術後の傷がなかなか治らず、感染リスクも高まります。
2. 感染しやすくなる
糖尿病によって免疫機能が低下するため、細菌感染に対しての抵抗力が落ちてしまいます。歯周病や口内炎、歯根の炎症などが悪化しやすく、通常なら数日で治るような感染も重症化する可能性があります。特に歯周病は「第六の合併症」とも呼ばれ、糖尿病との関連性が非常に深い疾患です。
3. 血糖コントロールが乱れると治療中のトラブルが増える
治療中の緊張や痛み、出血などによって血糖値が急変することがあります。低血糖発作を起こしたり、逆に高血糖による昏睡リスクが生じたりするため、安全な治療のためには血糖コントロールが安定していることが前提となります。

糖尿病の「程度」が重要な理由
糖尿病と一口に言っても、そのコントロール状況には大きな幅があります。血糖値の管理が良好な人であれば、基本的に通常の歯科治療を問題なく受けることが可能ですが、重度でコントロールが不良なケースでは治療そのものが制限されることがあります。
HbA1c値が重要な指標
歯科医院では、糖尿病の状態を把握するために「HbA1c(ヘモグロビンA1c)」という指標を参考にします。HbA1cは過去1〜2か月間の平均血糖値を示すもので、一般的には7.0%未満がコントロール良好とされています。
- HbA1c 6.5%未満:良好なコントロール状態。大半の治療が可能。
- HbA1c 7.0〜8.5%:軽度〜中等度のコントロール不良。治療内容に応じて注意が必要。
- HbA1c 9.0%以上:高度なコントロール不良。外科的治療は原則として延期される場合が多い。
このように、糖尿病の程度が歯科治療の可否を決める大きな要因となります。
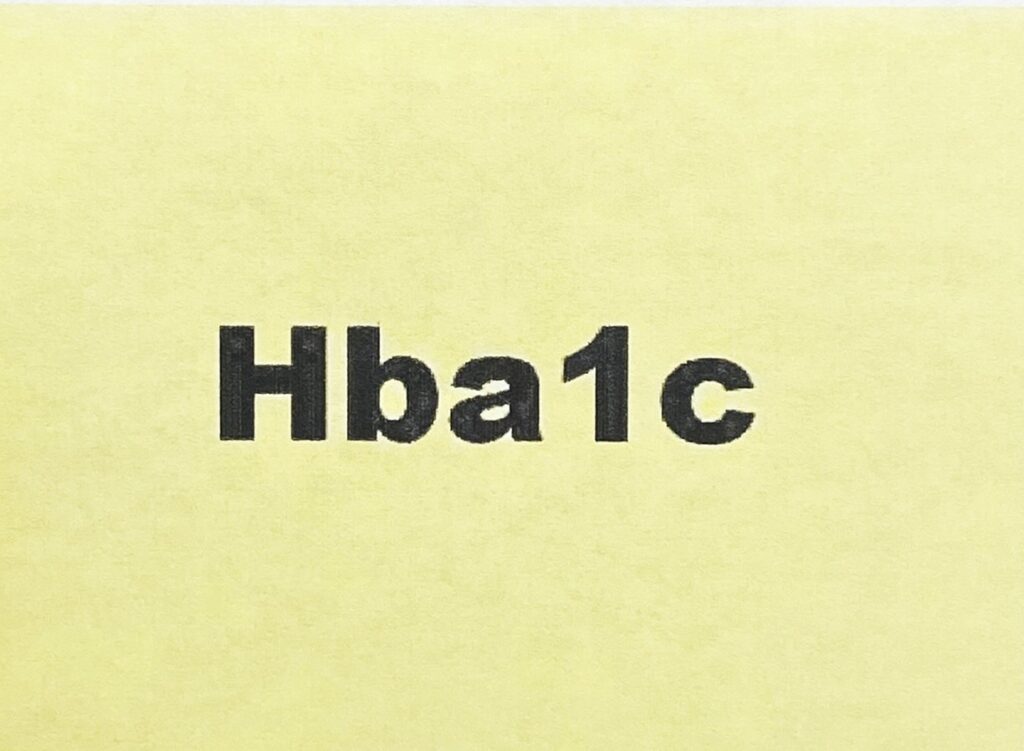
実際にあった事例:抜歯を断念したケース
60代の男性患者(糖尿病歴15年、インスリン治療中)は、右下の奥歯が大きく虫歯になっており、抜歯が必要と診断されました。しかし、術前検査でHbA1cが9.8%と高値で、さらに足に糖尿病性壊疽の既往があることが判明。歯科医師は抜歯による感染リスクと治癒不全を懸念し、内科主治医と相談のうえ、まずは糖尿病の改善を優先する方針となりました。3か月後、HbA1cが7.2%まで改善した段階で抜歯を実施し、術後経過も良好でした。
このように、糖尿病がコントロールされていない場合には、たとえ治療が必要であっても、あえて延期する判断がなされることがあります。

歯科治療前にできること
糖尿病患者が安心して歯科治療を受けるためには、以下の点に注意が必要です。
- 主治医と歯科医師の連携:糖尿病の主治医と歯科医師が情報を共有し、最適な治療計画を立てることが大切です。
- 最新のHbA1c値を提示する:歯科受診時には、直近の血液検査結果を持参しましょう。
- 低血糖に備えた対応:治療前に食事をきちんととる、ブドウ糖などを持参するなどの準備も重要です。
- 口腔内のセルフケアを徹底:糖尿病によって歯周病が悪化しやすいため、日常的なブラッシングや歯間清掃を徹底する必要があります。
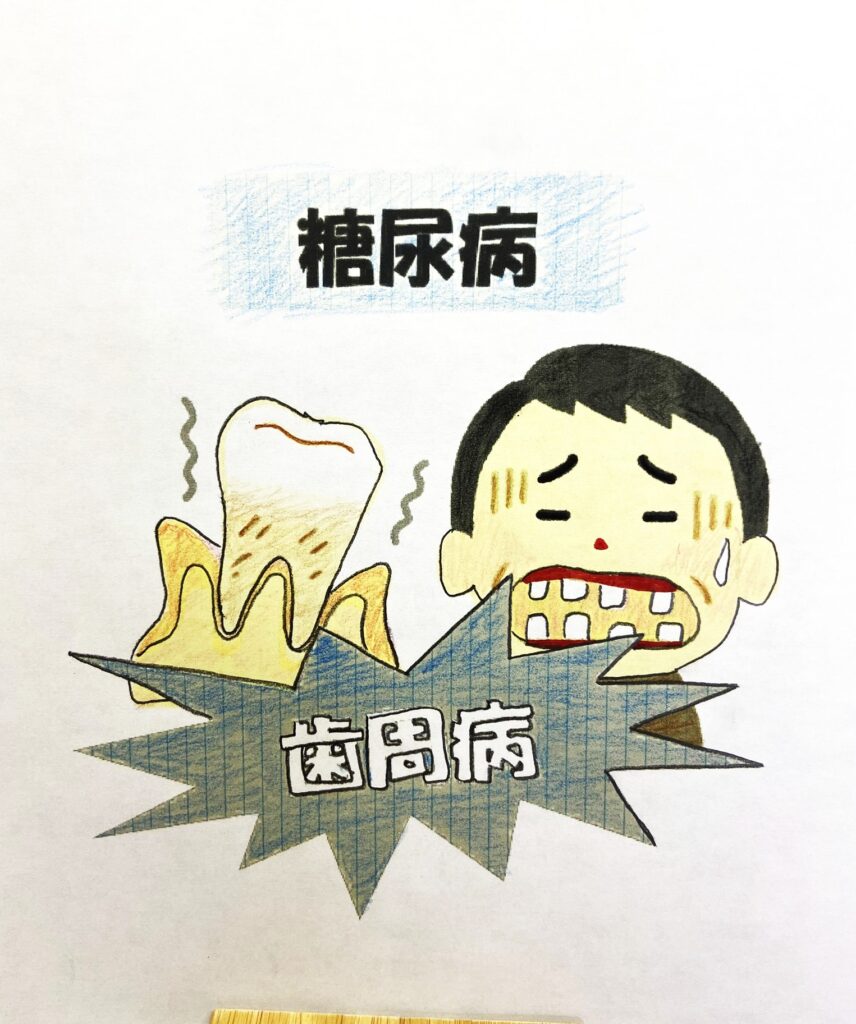
まとめ
糖尿病は、血糖コントロールの状況によっては、通常の歯科治療が制限される可能性がある疾患です。特に外科的処置(抜歯、インプラント、歯周外科など)では、感染や治癒不全、術中の血糖変動といったリスクを伴うため、十分な注意が必要です。
その一方で、糖尿病の患者こそ定期的な歯科ケアが必要であることも忘れてはなりません。放置すれば、歯周病が進行して全身状態に悪影響を及ぼす可能性もあるからです。
重要なのは、「治療を避ける」のではなく、「治療に備える」ことです。主治医との連携、日々の健康管理、口腔ケアの徹底によって、安全で質の高い歯科治療を受けることが可能になります。

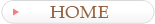
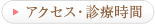
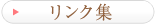


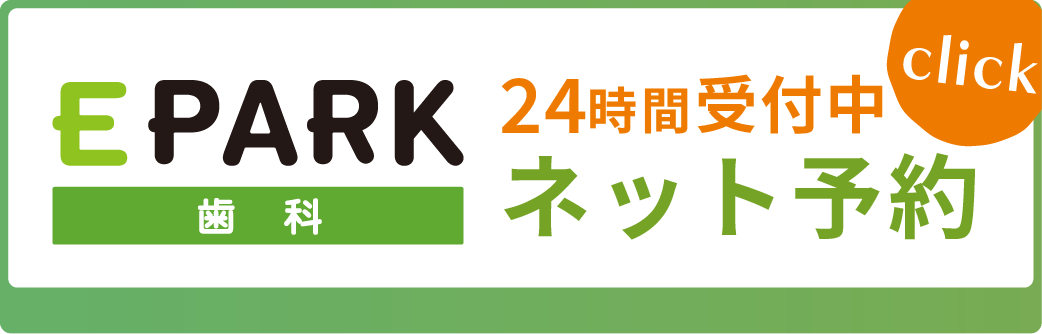

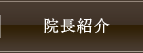
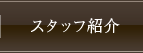
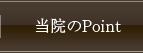
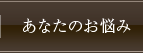
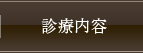
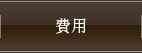
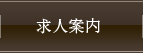

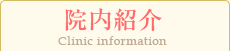


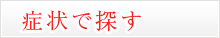
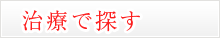

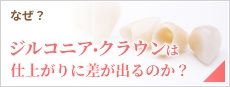


 当院のInstagramはこちら
当院のInstagramはこちら